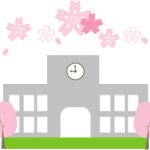仙台のずぼラク収納アドバイザー、はやさか ひろみです(o^-^o)
整理収納とライフオーガナイズで暮らしをラクにここちよくするお手伝いをしています。
わが家の子供たちがお世話になっている保育所で、おもちゃの収納を見せていただきました。
普段も送迎のときに気にしてみていて、工夫がいっぱいだな〜と思っていたのですが…
保育所の先生としてはお悩みもあるようで、見せていただきながらアドバイスもさせていただきました。
はじめはホール(所内で一番広いスペース。発表会などもここで行われます)のおもちゃ収納。
主に以上児さんが、ホールでいろいろなおもちゃを使って遊びます。
おままごとと、ブロック系と…など、そのときによって出すおもちゃは先生が決めるそうなのですが、
年齢も様々、男女混ざって遊ぶので、偏らないようその都度選んでいるようでした。
出すのも戻すのも、途中までは子供たち・あとは先生方(子供たちだけで最後までできるものもあり)。
どの段階に、誰のやりやすさを優先させるのか?をしっかり考えた方がよさそうです。
まず!
何と言ってもラベリングです。

さすが保育士さん。
文字と絵、両方で表してあるので、文字が読めないお子さんなどでもとってもわかりやすい。
それから、パズル収納。

わが家でもやっていますが、100均などによくあるケースを使って収納されています。
それぞれのピースの裏には同じマークが書いてあって、バラバラになっても判別しやすい工夫がされています。
それでもピースがなくなったりしちゃうんですよね〜と先生。
半端なピースがちょい置きされていた(これは大人の仕業らしい、笑)ので、ケースに戻すためにひとつひとつのケースを見て探していました。

よく聞いてみると、いつもパズルを出すときはせいぜい6セットくらいだそう。
でもこちらには20セットくらいは収納されていたので、その全ての中から探さないとちょい置きピースが戻せません。
→イライラの元…ですよね。
ちょい置きしちゃう大人にもやりやすいようにするには…?
1軍(よく使う)パズルと2軍(あまり使わない)パズルをわけてみることをご提案いたしました(*゚▽゚)ノ
こちらの保育所は子どもの人数も多いので、おもちゃの数も結構多いのですが、
『考えてみたら、あまり使っていないのもある…』
とのこと。
これを期に、ちょっと見直してみよう!ということになったようです。
今回、ブログ等で紹介させていただくこともご快諾いただきました。
本当にありがとうございます。
②へつづきますo(*^▽^*)o